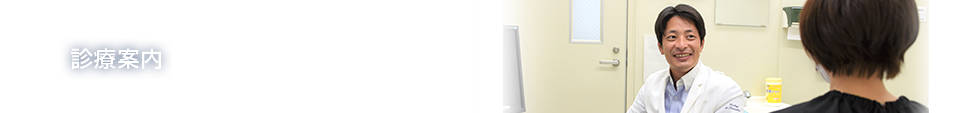腫瘍
腎細胞癌
はじめに
腎臓は左右に存在する、そらまめに似た形をした長径10cm程度の臓器で、血液をろ過し、尿を作ります。腎臓に発生する腫瘍として最も多いのが腎細胞癌です。(なお、腎盂癌については別項を参照下さい)
腎細胞癌(以下腎癌とよびます)は男性に発生しやすく男:女=2~3:1で、50歳以上に多い癌です。
症状・診断
代表的な症状としては、血尿、側腹部痛などがあります。しかし近年では集団検診や人間ドックでの超音波検査で無症状のうちに小さな腎癌が早期発見されることが多くなっています。また別の病気の精査中にCTや超音波検査によって発見される場合もあります。
腎癌と鑑別するべき疾患としては、腎嚢胞(のうほう)、良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫が代表的なものとして挙げられますが、その他にまれな腫瘍もあります。一般的に腎臓の充実性(中身のつまった)腫瘍がみつかった場合約90%が腎癌といわれています。もし、健康診断などでそのような指摘をうけたら、是非詳しい検査を受けて下さい。
腎癌が発見された場合、泌尿器科でこの病気の周囲への広がり、転移の有無について検査を行い、治療方針を決定します。
治療
治療の基本は外科的切除術(腎摘除術)です。仮にすでに転移があっても腎臓を摘出するのが一般的です。残念ながら、化学療法(抗癌剤)は有効ではないとかんがえられています。放射線療法もごく一部の例外(脳転移や骨転移)を除き、行われません。
腎癌の治療といえば、従来は開腹による根治的腎摘除術(腎臓+周囲脂肪組織+副腎摘除)が標準的な手術方法でしたが、最近では可能であれば腹腔鏡を用いた腎摘除術が行われることが増えています。
小さい腎癌に対しては、なるべく腎を温存し、腫瘍部分のみを切除する手術が試みられています(腎部分切除術あるいは核出術)。
手術療法
4cm以下の腎癌
基本的に腎部分切除術、核出術を行いますが、腫瘍の存在部位などにより腎摘除術が行われることもあります。開腹手術が基本ですが、最近では後述する腹腔鏡手術も行っています。
4-7cmの腎癌
原則的に腹腔鏡を用いた腎摘除術を行いますが、腫瘍の進展具合により開腹手術を行うことがあります。
7cmをこえる腎癌
原則的に開腹による腎摘除術を行います。
腹腔鏡下手術について
われわれは、適切であると考えられる腎癌に対しては腹腔鏡下手術をおこなっています。大きく開腹しませんので手術による体の負担が軽く、創の痛みもすくないため、回復が早いのが特徴です。ただし、大きな癌に対しては適応にはなりません。
腎静脈や大静脈進行した腎癌
腎静脈や大静脈進行した腎癌でも遠隔転移していなければ、根治手術による5年生存率は35~60%と考えられています。われわれはこのような腎癌に対しても積極的に手術を行っています。
手術以外の治療法についてですが、さきに述べましたように、抗癌剤や放射線を用いた治療は残念ながら有効ではありません。また、局所の治療として血管塞栓術やラジオ波による焼灼術もありますが、一般的とはいえません。
腎癌には免疫療法と呼ばれる治療法があります。免疫療法ではインターフェロン( IFN)、インターロイキン2(IL-2)が用いられます。主として転移や再発のある方に対して行う治療法ですが、その効果は20%くらいと満足のできるものではないのが現状です。
現在、世界中で転移のある腎癌にたいする治療法の開発が進められていますが、いまの時点ではまだ実験段階の域をでません。
最後に
一般的に4cm以下の腎癌の予後は比較的良好です。早期発見が重要な癌ですので、腹部超音波検査を受ける際は、腎臓も調べてもらってください。
腎癌は手術後10年以上経ってから再発することがあります。担当医師の指示があるまで通院は自己判断でやめないで下さい。
腎盂と尿管の癌
はじめに
癌が腎盂という腎臓の尿を集める部分の内側を覆う細胞にできたり、腎臓から膀胱(ぼうこう)へ尿を運ぶ尿管という細い管に発生したりすることがあります。腎盂と尿管の癌は、それ以外の腎組織や膀胱にできる癌よりはるかに少なく、米国での発症者数は毎年6000人未満とされています。また腎盂と尿管にできる腫瘍はそのほとんどが悪性で、良性腫瘍ができるのは比較的稀です。
症状・診断
多くの場合、肉眼的な血尿がみられます。また、癌によって尿の流れが妨げられると、わき腹または下腹部に激しい痛みが生じます。
肉眼的な血尿がある場合、腎盂と尿管の癌よりも頻度の多い膀胱癌の存在を疑い、膀胱鏡検査が頻繁に行われます。腎盂と尿管の癌の多くは静脈性尿路造影または逆行性尿路造影を行って診断します。CT検査は腎臓結石と癌や血液のかたまりと鑑別するのに役立ち、癌の進行度やリンパ節転移の有無がわかります。尿細胞診検査によって、尿中に癌細胞が見つかる場合もあります。
治療
癌が腎盂や尿管にとどまり転移していなければ、癌がある側の腎臓全体と尿管の全長を外科的に取り除く腎尿管全摘術を行い、同時に膀胱の一部も切除するのが一般的です。
腹腔鏡下手術について
われわれは、この方法が適切であると考えられる腎盂や尿管の癌に対して腹腔鏡下(後腹膜鏡下)手術をおこなっています。大きく開腹しませんので手術の負担が軽く、傷の痛みもすくないため、回復が早いのが特徴です。
癌の状態や癌のない側の腎臓の機能によっては、レーザーで癌細胞を破壊する治療や、尿管のうち癌の部分だけを取り除く手術で治療する場合もあります。
癌が転移していれば化学療法を行います。
手術後の外来通院について
この癌になった人は手術後に膀胱に癌ができるリスクがあるため、手術後は膀胱鏡検査を定期的に行い、膀胱に癌ができていないかどうかを調べます。
前立腺癌
前立腺癌とは
前立腺は男性のみに存在し、精液の一部を作る臓器で男性ホルモンに依存しています。膀胱の下側で尿道を取り巻くように存在し、後方では直腸と接しています。
前立腺癌はアメリカでは男性の癌の中で最も頻度が高く、死亡率でも2番目に多い癌です。日本人は欧米人に比べ前立腺癌と診断される頻度は低いのですが、食生活の欧米化の影響か、その頻度は増加してきています。また、健診などで採血によるPSA検査が普及してきたため、早期の段階で発見される前立腺癌が急激に増えてきました。そのため、さまざまな治療法が選択できるようになってきました。しかし、現在日本人男性の癌のうち死亡率の増加がもっとも著しいのは前立腺癌です。今後さらに若い年齢でのPSAのスクリーニング検査の普及が望まれます。
発癌の原因は不明で、他の癌でいわれているような食事・喫煙・感染などと前立腺癌の関係はまだ証明されていません。
PSA高値と指摘された方へ
PSAとは前立腺特異抗原(Prostate Specific Antigen)の略です。前立腺癌特異抗原ではなく、正常の前立腺の細胞も癌細胞と同じようにPSAを産生しています。したがって、PSA値だけで癌と診断することはできません。正常値に関しては、議論の残るところですが、一般的に4ng/ml以下と考えられています。しかし、年齢や前立腺の大きさなどでも違ってきますし、同じ人でもその時によって値の変動があります。前立腺に炎症がある場合などはかなり高値になります。血中のPSA値が測定されますので、癌組織では正常組織に比べ血中にPSAが出やすいため、前立腺癌が存在するとPSAは高い値を示す傾向があると考えていただければよいと思います。
現時点ではMRIや超音波などの画像検査で前立腺癌の確定診断を行うことはできず、診断は前立腺の組織を針で複数ヵ所採取(前立腺生検)して病理学的に癌細胞の存在の有無を確認する以外ありません。そこでPSA値より判断し、前立腺癌の疑いが高い方には前立腺生検を受けていただくことになります。PSAが4~10ng/mlで前立腺生検が施行された場合、癌が検出される確率は20~30%、10~20ng/mlで約50%、20ng/ml以上になると約80%といわれています。
骨に転移がない限り前立腺癌には特有の症状がないため、排尿困難や頻尿などの症状が生検の適応を決める判断材料となることはありません。
前立腺生検は肛門より超音波の機械を挿入して前立腺を画像的に確認しながら、直腸または、会陰部より針を刺して組織を採取します。採取方法、採取本数、麻酔法などは各施設によって様々です。検査後出血や熱発の可能性もあるため、当科では入院していただき施行しています。
画像検査はあくまで生検における癌の検出率を上げるために行う検査であって、癌の診断を行う検査ではありません。画像検査で異常を指摘された部位を積極的に生検で採取し、癌の検出率を高めていくことを目的としています。反対に、画像検査で異常が認められないからといって、生検を受けなくてもいい理由にはなりません。当院では本年より最新式のMRIが導入され、前立腺癌の検出感度を少しでも高めるべく、積極的に利用していく予定です。
前立腺癌と診断された方へ
前立腺癌は比較的進行が遅い癌といわれていますが、中には急速な進行を示す悪性度の高い癌が存在することも事実です。一般論で判断せず、各症例に対ししっかりとした治療戦略を立てることが必要です。きちんとした治療戦略を立てれば比較的予後は良好で、癌が前立腺内に限局している場合の5年生存率は90%以上、癌が前立腺の周囲まで拡がっていても転移がない場合は60~80%、リンパ節転移のみの場合は40~50%、骨など他臓器など遠隔転移を有する場合は20~30%です。
前立腺癌の治療法は一般的に、ホルモン療法、外科療法、放射線療法の3つです。そのほかに、最近では一部のごく早期の前立腺癌に対して、治療をせずに様子をみる待機療法やホルモン療法が効かなくなった症例に対する化学療法などさまざまな治療法の選択が可能となってきました。 我々の施設では、特殊な放射線療法以外はすべて保険診療のオプションを設えています。以下にそれぞれの治療法に関して簡単に説明します。
1 ホルモン療法
前立腺癌の大半は男性ホルモンの作用を受けて増殖しています。従って、男性ホルモンの働きを抑えこむことによって、癌が縮小することが知られています。体内における男性ホルモンは、脳内の視床下部や下垂体からの刺激によって主に精巣 (90-95%)、一部副腎 (5-10%) から分泌されます。前立腺癌におけるホルモン療法とは男性ホルモンを抑制する治療法で、男性ホルモンの産生を抑制する方法と男性ホルモンの作用を抑制する方法に分けられます。前者は、精巣からの男性ホルモンの産生を抑えるために両側の精巣を手術で取り除く方法(去勢術)と皮下注射(LH-RHアゴニスト)をする方法があります。効果は両者同等です。後者は、抗男性ホルモン剤によって男性ホルモンがその受容体に結合することを抑えます。去勢術またはLH-RHアゴニストでは抑制されない副腎から産生される男性ホルモンの作用を抑える目的で、去勢術またはLH-RHアゴニストに併用して投与される事 (完全男性ホルモン遮断療法)が一般的です。
副作用としては、男性ホルモンが減少するため活力の低下、女性化乳房、女性の更年期障害のような突然の発汗やほてり感、ED(勃起障害)などが生じたり、肝機能障害が起こることがあります。
ホルモン療法は、治療開始後はとても有効ですが、時間が経過すると効きにくくなり、生き残って再び増殖してくる癌が発生してきます。したがって、ホルモン療法だけでは、癌を根治的に治すことは困難と考えられます。そして、このホルモン療法が効いている期間は癌の悪性度、進行度などによって異なり、1年以内に効かなくなる人がいれば、数年以上効いている人もいます。
2 外科療法
手術によって前立腺自体を取り除いてしまう治療法です。前立腺癌は正常の前立腺組織中に入り混じって存在するため、腫瘍のみ切除することはできず、前立腺自体を切除します。前立腺を切除すると尿道と膀胱が離れ離れになってしまうため両者を縫い合わせます。手術中の合併症としては、出血、直腸損傷があり、輸血や一時的な人工肛門を要することがあります。
阪大病院では昨年輸血が必要となった症例は3.9%で、一時的な人工肛門造設が必要となった症例は1例もありません。術後の合併症は尿失禁とEDです。尿失禁に関しては術後1年以上経過した時点で、パットが1日1枚以内で十分な症例が95%以上を占めます。EDに関しては、前立腺のわきを走行する勃起神経を前立腺と共に切除することにより生じます。癌の根治性を考えた場合、勃起神経の切除は避けられないこともありますが、勃起に関する神経を温存しようと手術を行った場合、当科では約半数の方が術後勃起機能を認めています。
その他、限局性の前立腺癌に対する低侵襲治療を目指し、腹腔鏡下前立腺摘除術や関連病院において高密度焦点式超音波(HIFU)も行っています。関心のある方は外来診察時にご相談下さい。
3 放射線療法
放射線により癌細胞の根治を目指す治療です。方法として、阪大病院では、外照射、高線量率小線源治療、組織内密封小線源療法の3種類の治療法を行っております。
外照射は体外から放射線を前立腺に照射します。1日1回照射し、約2ヶ月の治療期間が必要です。
高線量率小線源治療は会陰部より前立腺に針を一定期間留置し、前立腺の内部より照射する方法です。1日2回、合計5日間施行します。入院が必要です。
永久線源体内埋め込み療法は放射線の線源を前立腺の内部に埋め込み、内部より照射する方法です。施行は1日ですみますが、施行後1日の入院が必要です。
それぞれの方法に利点と欠点があり、すべての患者様に適応となるわけではありません。詳しくは、放射線治療科のホームページをご参照ください。
放射線療法の副作用は放射線が原因となる皮膚炎による痛みや膀胱炎による排尿時痛、頻尿、血尿、腸炎による直腸からの出血などがあります。また、尿道狭窄が起こることもあります。放射線による副作用は、治療施行後長期間経ってから出現することがあるのも特徴です。
4 待機療法
何も治療を行わず経過をみるという選択肢です。
前立腺癌は比較的進行の遅い癌が多いこと、高齢者で発見されることが多いこと、また、ホルモン療法や放射線療法などが有効であることから、一部の前立腺癌に関しては、十分な観察下に無治療で経過をみることが可能であるとの考えに基づいています。
5 化学療法
一般的に前立腺癌に抗癌剤を用いた化学療法は有効ではありませんが、ホルモン治療に抵抗性となった癌には一部有効です。一部のステロイド剤には前立腺癌を抑制する効果があることも報告されており、当科ではいち早く、ステロイド剤と抗癌剤を用いた治療法をホルモン治療が無効になった症例に対し取り入れ、現在では外来通院でこの治療法を施行しています。
病期と病期別治療法
それぞれの病期により、治療法の適応は異なります。以下に病期と病期別治療法を列挙します。しかし、前立腺癌の悪性度など個々の症例により治療法の選択肢も若干変わってきますので、詳しくは主治医にお尋ねください。なお、わかりやすくするために病期分類は原文とは少し異なる箇所もあります。
病期(TNM分類)
原発腫瘍(T)
- Tx:原発腫瘍の評価が不可能
- T0:原発腫瘍を認めない
- T1:臨床的に不顕性であり、かつ触診によっても画像によっても腫瘍が認められない
- T1a:偶然に検出された腫瘍で切除組織の5%未満
- T1b:偶然に検出された腫瘍で切除組織の5%を超える
- T1c:針生検で腫瘍が同定される(例えば、PSA値の上昇により)
わかりにくい表現ですが、つまりT1aとT1bは前立腺肥大症に対する手術が施行され、病理組織検査にて前立腺癌が見つかった場合で、T1cは検診などでPSA高値が指摘され、触診や画像検査では癌が指摘されなかったが、生検を施行したら前立腺癌が見つかった場合をさします。
- T2:腫瘍が前立腺内に限局している
- T2a:腫瘍の浸潤が1葉の半分以下
- T2b:腫瘍が1葉の半分を越えて拡がるが、両葉には及んでいない
- T2c:腫瘍が両葉に及んでいる
これまた、わかりにくい表現ですが、つまり癌が右か左のいずれの側にのみ存在する場合がT2aまたはT2b、左右両方に存在する場合がT2cとなります。さらにややこしいことに、この場合の癌の存在部位の診断は触診か画像検査によってなされたものであるということです。つまり、PSAが高値で生検が施行され、左右両方から癌が検出されても、触診や画像検査で異常が認められなかった場合はT1cと分類されます。
- T3:腫瘍が前立腺被膜の外に進展している
- T3a:被膜の外へ拡大
- T3b:腫瘍が精嚢へ浸潤
- T4:腫瘍が精嚢以外の隣接臓器(膀胱、直腸、骨盤壁など)への浸潤している
所属リンパ節(N)
- Nx:リンパ節に対する検査がなされていない。
- N0:リンパ節転移を認めない
- N1:リンパ節転移を認める
この場合のリンパ節とは前立腺の近傍の骨盤内の所属リンパ節を指し、それ以外のリンパ節に転移を認める場合はM1aとなります。
遠隔転移(M)
- Mx:遠隔転移の評価が不可能
- M0:遠隔転移を認めない
- M1:遠隔転移を認める
- M1a:所属リンパ節以外のリンパ節
- M1b:骨
- M1c:骨転移を伴う、または伴わないその他の部位
病期分類別治療法
1) 転移がない場合T1~2 N0 M0
積極的な治療を行わず、経過観察
ホルモン療法
外科治療
放射線療法
外科治療または放射線療法 + ホルモン療法
T3 N0 M0
- ホルモン療法
- 外科治療 + ホルモン療法
- 放射線治療 + ホルモン療法
ホルモン療法
- 放射線療法 + ホルモン療法
ホルモン療法
膀胱癌
膀胱癌の疫学
膀胱癌の発生頻度は毎年人口10万人あたり約17人と、それほど多いがんではありませんが、最近わずかですが増加傾向にあります。男性に多く、女性の約3倍といわれています。多くは40歳以上で発症しますが、まれに若年者で発症することもあります。
膀胱癌の発癌に化学染料など一部の化学薬品が関与しており、それらを扱う職業従事者に膀胱癌の頻度が高いことがわかっています。また、喫煙者は非喫煙者の2~4倍の割合で膀胱癌になりやすいことも示されています。
食べものに関しては様々な報告がありますが、現時点でははっきりと証明されたものはありません。
3つのタイプの膀胱癌
膀胱癌は大きく3つのタイプに分けられます。いずれも主たる症状は、血尿(痛みを伴わない)や膀胱炎様の症状です。
1 表在性膀胱腫瘍
新たに診断された膀胱癌の約70~80%はこのタイプです。多くは無症候性血尿で見つかります。腫瘍が膀胱の内腔に向かって突出して存在しますが、腫瘍の根は粘膜下にとどまっているものです。経尿道的な内視鏡手術で切除可能です。しかし、約60%は再発するため、治療後も厳重な経過観察が必要です。膀胱内に抗癌剤やBCGを注入することで再発率を下げることができます。ほとんどの場合は再発しても次に示す浸潤性膀胱癌になることはないので、再発しても内視鏡の手術ですみます。5年生存率は95%と良好です。
2 浸潤性膀胱腫瘍
腫瘍が膀胱の筋層や筋層を超えて浸潤しているもので、内視鏡の手術のみでの治療では不十分な場合がほとんどです。その場合は、膀胱全摘除術や放射線療法や抗癌剤による治療が必要となります。5年生存率は25~80%と腫瘍の浸潤具合により様々です。
3 上皮内癌
隆起した腫瘍の形態をとらず、膀胱内腔を粘膜に沿って進展するタイプの腫瘍です。このタイプは頻尿や排尿時痛の様な膀胱炎症状をきたすことが多いです。他臓器の上皮内癌が前癌病変であるのに対し、膀胱の上皮内癌は悪性度が高く、浸潤性膀胱癌に進行する可能性が高いため、厳重な治療が必要です。多くは膀胱内への薬物注入療法をまず行うことになります。
転移のある膀胱腫瘍は非常に予後不良で、5年生存率は20%以下です。しかし、最近新しい抗癌剤治療の成績も報告され始め、当科でも治療成績の改善を目指し、患者様のQOLを重視しつつ、様々な治療法を行っています。
転移のない膀胱癌の治療
1 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)
尿道より内視鏡を膀胱内に挿入し、電気メスで腫瘍を切除する方法です。腫瘍の大きさや個数によりますが、手術時間は1時間くらいです。術後数日間、尿道カテーテルの留置が必要となります。
2 膀胱全摘除術
浸潤性膀胱癌や膀胱内注入療法が無効である上皮内癌が適応となります。通常は膀胱と一緒に、男性の場合は前立腺と精嚢を、女性の場合は子宮を一緒に摘出します。尿道を切除するかどうかは個々の症例により異なります。当科での膀胱全摘除術の治療成績を示します。(表1)海外の有名な施設の成績と比べても、同等かやや優れた成績です。
表1.膀胱癌の癌特異的生存率 (海外の施設の治療成績と比較)
| 症例数 | pT2 | pT3 | |
|---|---|---|---|
| 施設 A | 58 | 72% | 40% |
| 施設 B | 99 | 62% | 57% |
| 施設 C | 202 | 75% | 19% |
| 施設 D | 197 | 64% | 44% |
| 施設 E | 160 | 76 | - |
| 施設 F | 71 | ~80% | - |
| 施設 G | 227 | 79% | 36% |
| 施設 H | 101 | 84% | 56% |
| 施設 I | 1026 | 66% | 31% |
| 施設 J | 369 | 63% | 33% |
| 阪大 | 53 | 80% | 54% |
 ご挨拶
ご挨拶